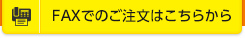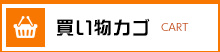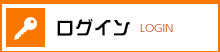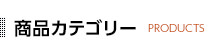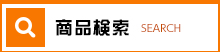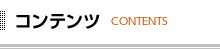世説人語
円安の裏へ・・・その一
1998年(アジア金融危機)以来、24年ぶりの円安水準とよく伝えられていますが、当時も1997年に米国の利上げで、大量のドルがアメリカに戻り、ドルを中心とした外貨準備高が少なかった韓国、タイ、香港などが、米ドルの本国回帰によってタイの通貨パーツ、韓国のオン、香港ドルも大幅の通貨安になって、アジア金融危機を誘発しました。日本もその影響で円安になりました。
では20数年後のアジアの経済規模も各国の外貨準備高もだいぶ増えたのですが、韓国のオン、日本円も、イギリスのポンド、いやこれだけではなく、ユーロまでも通貨安になっています。米国の金利水準までに上げて、外貨を本国から逃げることを回避することもできますが、コロナ禍の経済不況で、企業や暮らしの支援に大型の国債の発行や銀行融資のコストアップにも警戒しなければなりません。ジレンマの中に金融政策で対処する選択肢もほとんどありません。
1998年も2008年の金融危機を巻き起こした起因はいずれも米国の利上げで、国際機関投資家の「投機売り」によるもの、その構図は今回も変わりません。もっと遡れば、1989年日本のバブル崩壊も2001年のアルゼンチン通貨危機も、背後にその投資勢力の暗躍があったからです。
では、円安の裏に何があったのか、国際機関投資家はどういった手段で「投機売買」で主権国家の通貨安を齎し、自分の財布を充填しているのでしょうか。その手の内を見てみましょう。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
「Zoom」の発端は?
パンデミックで、コロナという見えない敵を相手に、原始的とは言え、物理的に人間同士の接触を遮断することはもっとも有効な手段とされています。飲食店のテーブルに客と客の間に隔ている透明アクリル板は、その典型的なグッズで、マスクと一緒に今の時代象徴となっています。
もちろん現代社会においては、ロックダウンなどの強力的な手段を講じる時に、基本的な人権や適度な自由、経済影響などのバランスも考慮することも言うまでもないことです。そこでテレワークやビデオカメラなど、非接触というキーワードから生まれた仕事パターンやビジネススタイルが定着してきました。ネット会議、ネット講義、オンライン授業、オンライン面接などの需要が高まり、「Zoom」というソフトウェアが一躍脚光を浴びるようとなりました。
ビデオ会議システム「Zoom」の創業者は中国山東科学技術大学出身の袁征という人物です。同大学卒業後、ビル・ケイツの講演に感銘を覚え、以前から構想していたビデオ通話システムの開発のため、米国に渡りました。当時の本人は英語が苦手で、短期間で英語を習得するため、食事と睡眠以外の時間をすべて語学学習に費やしたそうです。
シリコンバレーで同じ中国出身の朱敏が作った会社WebExに入り、エンジニアになりました。2007年、WebExがシスコシステムズに32億ドル(約3520億円)で買収をされました。袁征も自動的に移籍となり、総勢800人の開発チームを率いるマネージャーとなりましたが、2011年にシスコシステムズの方針に合わない理由で、退社し、Zoomを起業することとなります。
「Zoom」の発端は、袁征が切実な願望から開発されたもので、同氏は大学時代に遠距離恋愛をしていたため、遠距離恋愛をしている恋人同士のために開発したツールでした。しかし、恋愛のツールとしては広かりませんでした。2013年頃、袁征は法人需要に着目をし、ビジネス会議システムとして、売り出しました。シリコンバレーでリモートワークが普及するとともに利用者数も多く伸びました。
そして、周知の通り、2020年のコロナ禍で、「Zoom」がビジネスにおいて必須のツールとして、爆発的に普及を成し遂げました。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
石油消費大国(下)
第3位 インド
毎日の石油消費量は2000年の中国と同レベルで、465万バレルです。1990年の117万バレルから、2000年の218万バレルに毎日の平均消費量が増えました。2010年は314万バレルに達していました。インドも産油国の一つですが、油田資源の枯渇や投資不足、生産量は毎日平均89万バレルに止まっています。今後の人口増加や経済発展など、石油の需要が大きく見込まれているので、ますます輸入に頼らざるをえません。2040年に毎日の石油消費は恐らく870万バレルまで膨らむと予測されています。
第4位 ロシア
消費量は一日平均で361万バレル、世界の4位になりますが、米国、サウジアラビアに次ぎ、世界3番目の産油国です。一日1078万バレルの原油を生産し、世界の生産量の11.28%を占めています。年間生産量の45%は輸出に回しています。輸出量もサウジアラビアに次ぎ、2番目になります。ウクライナ侵攻で、西側からの制裁はロシア今後のエネルギ事情にどういう風に影響を及ぼすかは分かりかねますが、注視する必要があります。
第5位 日本
毎日消費量は343万バレルで、世界5位の石油消費大国です。1970年代の経済発展で一時的に原油の消費をエネルギ全体の80%に達しましたが、2019年にその割合は40%まで落ちました。1999年の毎日石油の消費は560万バレルでしたが、2010年は440万バレルに減りました。予想では2022年は毎日341万バレルの消費で、2023年は339万バレルになると減り続けています。石油からLNGガスへの切り替えは主な理由ですが、ハイブリッド車の普及や少子高齢化など社会全体の需要減も大きな要因になるのではないでしょうか。石油の供給国は主に中東の産油国で、輸入量の90.5%を占めています。サウジアラビアは45%、アラブ首長国連邦(UAE)は25%、残りはカタールやクウェートなどです。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
石油消費大国(上)
石油は石炭、天然ガスに並び、主なエネルギとして各国の経済や生活を支えています。上位5カ国は世界生産量の48%を消費していることをご存知でしょうか。
2021年、地球上に平均毎日9739万バレル(1バレルは約159リトル相当)が消費されていました。2022年は一日当たり9961万バレル、2023年は更に10155万バレルに消費が伸びるそうです。石油消費の上位5カ国の詳細は以下のようになります。
第一位 米国
世界消費量の20.31%を占め、最大の石油消費国になります。アメリカは消費国として、断トツの一位ですが、世界最大の産油国でもあります。2021年、米国の情報・エネルギ管理局(EIA)が公表した数字によると、毎日1877万バレルの生産量を誇ります。それに対して、米国の一日あたりの平均消費量は1990年の1699万バレル以来、2021年までそれほど増えていません。2022年は2051万バレルで、2023年は2078万バレルという試算があります。昨年にアメリカは73カ国から一日当たり847万バレルを輸入していましたが、毎日平均863万バレルを輸出しています。カナダ、メキシコ、ロシア、サウジアラビア及びコロンビアは主な供給国です。カナダは米国原油輸入量の62%を提供することになっています。
第2位 中国
世界の石油生産量の約16%を消費しています。米国に次ぐ第2番目の消費国になります。中国も主要な産油国ですが、生産量は消費量を大きく下回っているため、輸入に頼らざるをえません。1990年は毎日平均の消費量は233万バレルでしたが、2000年は469万バレル、2010年は499万バレルまでに増えました。2021年、国内石油生産量は一日あたり499万バレルに対して、一日の消費量は1527万バレルに達していました。2023年は1605万バレルの需要を見込まれますが、生産量は510万バレルと限定的になると専門家が指摘しています。2017年に、石油輸入量は米国を超えました。ロシアや中東の産油国は主な供給国になります。とくにロシアへの石油依存度が高く、ロシアの石油輸出量の20%を中国が買っているそうです。ロシア石油の対中国供給についてはパイプラインと海運の2通りあります、2021年ロシアから一日当たりの輸入量は160万バレルと伝えられています。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
RUSSIA TODAYの声
たまにロシアの生の声を聞いてみましょう。
5月15日に西側に声を封じられたロシアのメディア、ロシアトゥディ(RUSSIA TODAY)のウェブに「ロシア石油がなければ西側の生存可能か」と題し、文章を発表しました。
文章はいくつかの国や地域がロシアの代わりに石油の代替供給能力を分析しました。まずアメリカは石油を増産し、ヨーロッパへの輸出を強化するだろうが、米国産石油に含まれる炭素の量が低いため、ヨーロッパ市場のガソリンや軽油生産に向いていません。カナダは世界5番目の石油生産国で、三番目に埋蔵量の多い国ですが、石油パイプライン及びに輸出インフラ整備の欠如で、近くの北米市場へは運べますが、大西洋を隔てているヨーロッパに運ぶのが難しいです。中東地域は世界半分ぐらいの石油埋蔵量を誇っていますが、インフラ投資不足や政治衝突など地政学上のリスクがあって、特に対イラン制裁は中東の代替供給能力を妨げています。
中央アジアの大国カザフスタンも石油埋蔵量は豊富ですが、ロシアのパイプラインを経由していますので、ロシアからの許可がなければ、ヨーロッパへの流出ができません。
ヨーロッパにおいてはノルウェーがロシアに次ぎ、2番目の石油供給国になっていますが、供給量はロシアの1/3に過ぎず、新たに石油発掘を許可すると表明していますが、発掘ポイントの選定や開発など、喫緊のエネルギ課題として、ヨーロッパは待てません。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
ロックダウンによる入荷の遅延
お客様各位
いつもお世話になっております。
連日のニュースなどでご存じだと思いますが、上海及び周辺地域などのコロナ対策より、物流が滞っています。また、オミクロン株の毒性は弱いものの、その伝播力は尋常でないため、コロナの蔓延防止もゼロコロナ対策も難しくしています。強力的な手段で実施してきた「ゼロコロナ政策」はコロナ病原菌の少ない国内環境を作っていたため、65歳以上の老人のワクチン接種はほとんど推奨してないのが裏目に出ていると言います。物理的にコロナウイルスをシャッターオウトし続けなければ、試算によると数千万人の感染者と数百万の死者が出るそうです。
また、上海に限らず、北京や安徽省なども感染拡大の恐れがあって、「人命尊重」という大前提に異議を唱えませんが、サプライチェーンの支障や入荷の遅延が生じてるのも事実です。
現在、コロナを抑える状況を見ると、ロックダウンの解除は更に2、3週間必要なのではないかと思います。
弊社の欠品中の高圧平面プレス機、昇華転写B級白マグカップ、32mm磁石缶バッジパーツや品薄になっているタイル用木製額縁などの入荷は予定より大幅に遅れが出ています。コンテナの調達や港の選択、船の予約について中国側と積極的に交渉をした結果、上記貨物の輸入目途がつきました。入荷時期も今月末か来月上旬と推測します。
昨今のご時世で急な状況変化もあり得るので、万が一入荷の日程が延びる場合は、欠品待ちのお客様にお待たせして大変申し訳ありませんが、ご了承いただきたいと思います。
何卒宜しくお願い致します。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
情報の仕入先
ウクライナ侵攻から2ヵ月以上経ったのですが、西側のメディアは主に米国やイギリスから情報を仕入れて、ロシアが「悪」、ウクライナは「善」と連日風向きの決まった報道を繰り広げています。一方、もっと多くの国々は当事者でない中立的な立場で、この戦争に至る経緯や戦況をわりと客観的に見ています。インドやイスラエルのメディアや中東や南米のメディアはそうです。そのほか、幾つか独立系メディアは激戦地に赴き、ウクライナが民間人を虐殺しているとも報道されます。例えば、白人至上主義者らが創立した「アゾフ連隊」は親ロシア勢力に対抗するため、発足したのですが、初期の隊員は極右思想者が多かったので、西欧諸国やアメリカ下院も「ネオナチ」と認定していました。
独立系が戦争に巻き込まれた一般市民に手当たり次第に放置されている民間人の死体現場の近くに取材を行い、「自分たちを攻撃したのはロシア軍やドネツク人民共和国軍ではなく、「アゾフ大隊」だ。建物を砲撃し、破壊しているのも「アゾフ大隊」だ。」と口を揃えて、証言しました。
また、「「アゾフ大隊」は住民を避難させるといって家から出るように、集まった人々が避難を始めると、いきなり撃ってくる。これで大勢が死んだ」、「学校や病院、劇場などに内部から爆薬を仕掛けて破壊して、それをロシア軍の仕業にしたいようだ」、「「アゾフ大隊」は傷病兵の手当をするために病院を占拠し、入院患者や医者、看護婦の退去を命じた。逆らう者は容赦なく射殺された」、「ロシア軍は敵ではない。彼らは我々に物質を提供し、守ってくれている。敵はゼレンスキーとネオナチの「アゾフ大隊」だと数数の声で語ってくれています。
アメリカ人でチリ在住の映像作家、ゴンザロ・リラも西側の報道と異なる現実を見て、次のような報告をしていました。「ゼレンスキーは侵攻するロシア軍と戦うために、刑務所に収監されている凶悪犯に武器を渡して開放している。このため、彼らによるレイプ、殺人、店舗襲撃などが相次いでいる。ゼレンスキーはとんでもないことをしている。今すぐやめるべきだ」。
非常に残念ですが、現在、リラは滞在していたハリコフでネオナチの民族主義者に拘束、ないしは殺害されていたとも思われています。
伝えることの大切さは誰しも分かりますが、情報の信憑性がもっとも大事にしなければならないものです。世界分断の亀裂で、マスメディアも中立の立場から、政治の圧力なり自己検疫なり、情報の仕入先より陣営化されているように感じます。80年前、あの現実と異なる大本営発表を想起させてしまいます。
インターネットで情報量が爆発している時代において、政治方向によって感情移入された断片的な情報伝達に視聴者の認知や情緒をコントロールされる世の中になっているので、信憑性のある情報の摂取や選別は大変難しくなっています。従って、偏向的な伝えではなく、バランスの取れた情報摂取を目指すなら、情報の出処を常に考え、メディアの伝えを常に疑う姿勢が必要になるのではないでしょうか。場合によって、翻訳の機能を使って、海外のニュース、西側陣営以外の国々のニュースをチェックすることも有効な手段だと思います。
※上記文書は「MONEY VOICE」に掲載した「ウクライナ危機で「グレート・リセット」本格始動。ロシアが2月24日に軍事侵攻した本当の理由」(作者 高島康司)を参考や一部引用をしました。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
円安の正体(下)
経済界の試算で、円の価値は対ドルで120円前後まで安くなっても、何とか日本経済に大きな損害を与えず済みますが、120円、125円を超えると経済の立て直しは難しくなります。でも何故日銀は経済に悪いと承知したうえ、円安に介入しないでしょうか。
経済効果を狙うより、むしろ債務危機を救済することが大事というのが本音ではないでしょうか。1980年、日本の公共債務はGDP(国内総生産)の50%でしたが、1995年は90%になっていました。2000年は140%に達し、2005年は約190%、現在の水準は250%に上り、2009年頃の「ギリシャの債務危機」のレベルになっています。
量的緩和(通貨の超量発行)を続ければ、世に出回る超量の通貨が債務を希釈することができるのです。また、超量の通貨もより多くの国債の発行を容認しやすくなります。日本の国債は日銀や各銀行が買っているので、主に国民の預貯金から成り立っているため、この債務を希釈されるのは、根本的に国民が所有するお金の価値です。そうです、国民の預貯金の価値が減るのです。
2021年日本にGDPはほぼ5兆ドルになりましたが、直近の円安のせいで、海外の試算では事実上4.5兆ドルの経済規模になりました。世界4位の経済大国ドイツは2021年4.1兆ドル強のGDPを達成し、その勢いは後数年、3位の経済大国日本を超えるかもしれません。
円安が悪いと一概には言えませんが、その臨界点の把握は肝心です。1997年のアジア金融危機は米国の利上げで、資金は韓国や東南アジアから米国に戻ったことによって、始めていましたが、当時の日本も輸出強化のため、円安を続けました。結局、東アジアと東南アジアの同時通貨安を促してしまい、金融危機を広げました。
今回の円安は1997年よりもっと複雑な要因を潜めていますが、20数年間の経済成長で、東アジアも東南アジア諸国も金融危機への対応力が上がりました。円安で、海外の資金が国内から撤退します。日銀の量的緩和で、日本市場に貨幣の流動性を増幅しても、国内の資金も脱日本を加速すると思います。いわゆる「失血」状態に陥ります。「失血」により多くの「輸血」で補填するという悪いシナリオになりかねますし、全面的な危機を招く可能性もあるのではないでしょうか。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
円安の正体(上)
最近、円対ドルの為替レートは120円の大台を超え、125円にもなりました。130円や135円まで落ちるのではないかと経済界は危惧しています。米ドルの指数とリンクしている円は1ドル=120円は妥当なレートと認識されています。
円は安くなると、海外が日本製を買いやすくなり、輸出にいいかもしれませんが、日本の消費者は海外商品を購入する際より多くの支払いをしなければなりません。いわゆる通貨安による物価上昇が発生します。世界の基軸通貨のアメリカも国内救済のため、米ドルの量的緩和を続けてきたため、ドル安によるインフレは去年の5月から続いてきています。最近の数字は危険値の5%を超えて、7.9%に達しているそうです。石油、天然ガス、石炭、金属や農産品などの商品価値を米ドルで計るため、ドル安は必然的に価格高騰を齎しますし、地政学上のリスク(ロシアのウクライナ侵攻)も加えて、その値上げに拍車をかけました。まして、ドルに対して、安値を更新し続けている円です。円を使っている日本国民は物価高を余計に感じるはずだと思います。
1985年プラザ合意後、円の相場は10年間をかけて、250円~80円とほぼ3倍、円高が続きました。1995年~1998年の3年間、80円から150円に約半額、円安に転じました。その後の10年間の乱高下を経って、2008年、米国発の金融危機が発生した後、日本円はイギリスポンドに100%、アメリカドルに50%も価値が上がり、4年間、その価値を堅調に推移しました。その背景に20数年の間に、堅調な経済と好調な輸出が支えていました。
しかし、今回の円安は違います。国際貿易は3年間の収支赤字が続き、国内経済も回復の兆しが見えず、円を下から支えられる要因がなく、海外投資家もリスク回避の通貨として、円の価値をプラスに判断できません。しかも、米国内のインフレを対応するため、年内の米国の金利上昇を数回行うそうですが、日銀の黒田総裁は量的緩和を続けると宣言しています。「コスト高騰によるインフレは、収入増に繋がらないため、輸入業の利潤と家計が圧迫され、日本経済に損害を与えます。」とは理由のようです。円安は日銀が望んでいることになります。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同
ロシア製ガスをルーブルで支払え
西側諸国の制裁にプーチンも黙っていません。欧米・日本などの制裁側を「非友好国」と認定し、ロシアから天然ガスや液化天然ガス(LNG)を購入する際、取引代金をロシアの通貨ルーブルで支払えという大統領令に署名をし、4月1日から執行します。
ロシアの銀行をSWIFTから排除され、貿易の国際決済が難しくなる中、ヨーロッパのエネルギがロシア依存という現実があります。アメリアはロシア依存が3%しかなく、カナダの天然ガスもアメリカから輸入しているので、痛みもなにもなく米国追随はOKですが、イギリス、日本も8%ぐらいの依存度で、何とか対応はできるのです。しかし、結束すべくEUの国々は高い依存度で、もはや無傷で相手を苦しめることができません。ロシア製石油や天然ガスを買い続け、銀行間の送金で外貨決済の抜け道も作りました。ロシアのガス会社傘下のガスポロムバンクなど、制裁の対象から外しています。
G7はルーブル支払いはルール違反と見て、明確な反対をしていますが、ヨーロッパのエネルギ事情は、ロシア抜きで語れない現状がある以上、当面の間はルーブルで支払うためのロシアの銀行に特別口座を開設します。米ドルやユーロなどの外貨を特別口座に送金し、ルーブルに両替してから支払うことになります。
株式会社中和 ラッキー プリント 社員一同